子どもは勉強がキライだ。
自発的になんてまずしないのが普通。
片付けもキライだ。
散らかすのは得意だけど。
そもそも学校だって、基本的にはキライな子が多い。
時間管理、提出物や宿題、持ち物、計画、人の話を聞く……etc
できない。
もう!
困っちゃう!
……んだけど、できる子もいるのよね?
同じ年齢でできる子もいるのに。
やるべきことができない
例えばタスクの管理。
ウチの子、自発的になんてやるわけがない。
叱責宿題とか準備とか頭からすっぽ抜け、ゲームに熱中する我が子。
見ている親御さんがイライラ……。
イヤミや小言、強い叱責なんかで毎度ケンカになるくらいなら、いっそのこと
- 全部やってあげる
- 何もしない
の二択を僕はお勧めしてるんだけど。
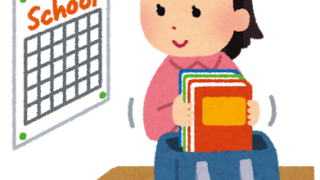
これさ。
「将来のために、少しずつでもやらせたい!」という親御さんの気持ちはとてもよくわかる。
そんな思いから、つい小言を言ったり、親のタイミングでブチ切れたり。
でも子どもの側から見ると、楽しくゲームしてたのに、突如ブラックホールから親の叱責が現れたわけで。
※この子は、ゲーム中は宿題の存在などブラックホールに消え去っている。
驚き、反射的に逆ギレする子ども。
その理不尽な反応にヒートアップする親。
そうして始まる泥仕合……。
外来でよく聞くシチュエーションだ。
これ。
(今は)出来なくていい
と僕は思っている。
このようなトラブルが多いのは、幼児〜4年生くらい(中学年以下)でしょうか。
この年齢だと多分、本質を理解していないから。
こんな心理実験がある。
外国の実験だ。
先生が、生徒たちにゲームのルールを説明する。
でも、実は提示されたルールではゲームが成立しない。
説明の段階でこれに気づくのは、5、6年生からなのだそうだ。
3、4年生くらいまではルールの不備に気づかず、とりあえずゲームを初め、途中で「センセーやっぱりこれじゃ出来ません!」ってなる。らしい。
この実験、僕は体感的にもこんなもんだと思っていて。
自分の頭で後先考えて判断できるのは、5、6年生以降。
うん、そんなもんだろう。
それ以前は、分かっていないのだ。
じゃあ、タスクの管理など出来なくて当然。
今宿題をやらないと、あとで大変になること。
勉強しないと、追い追いツケが回ってくること。
悪化してから尻拭いするより、今やっちゃった方がずっとラクなこと。
分かっていないのだ。
だもんで。
僕は基本的に、後先考えて主体的に行動できるのは小学校高学年以降と考える。
それ以前は、「出来ない」のだ。
目先のことしか考えられない年齢。
発達的に、そんなもん。
できる子の、できる理由
そうは言っても、こう思われるだろうか。
自分から、もしくは軽い声かけで動ける子。
そうね。
確かにいます。
じゃあ逆に、この子たちはなぜ「出来る」のかを考える。
個人的な意見だけどさ。
分かってないけど動いてる
と思うんだよね。
一部、知的に高く先まで考えられる子もいる。
でも、多くはない。
多数派は、怒られたくないから動いているに過ぎないだろう。
先まで考え、合理的に判断し、納得して動いているわけではない。
やらないと、怒られるから。
そういうもんだから。
それだけ。
本質は理解していなくても、目先の叱責を回避するために動ける子はいる。
「よくわかんないけどそういうものだから」宿題をやる。
やらないと怒られるし。
これは性格だ。
- 怒られないよう、ふわっと無難な道を選ぶ。
はたまた
- 怒られる覚悟で、納得しないことはやりたくない。
の、どちらか。
生まれつきの性格だろう。
世の中には、2種類の人がいるようだ。
世間の流れに抗わずにふんわりとその一生を終える人と、
納得できないとどうしても先に進めない人と。
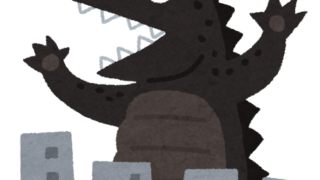
そして、本質的にはよく分かってないけどなんかふわっと動ける人。
これってそんなに尊い? と思う。
もちろん、波風立てず無難に世の中を渡っていくスキルは重要。
でもやっぱ、ゴールは本質を理解し、自分で考えて動くことだろう。
理解していないなら、結局「動く」か「動かない」かにさほど違いはないように思える。
そう考えると、上述の
- 言わなければ延々動かない。
- でも言ったらキレる。
タイプの子と、そこまで大きな差があるように思えない。
だから、まぁいいんじゃね? というのが僕の意見。
動けることが、そこまで素晴らしいとも思わない。(いや素晴らしいけども。手放しで大絶賛ってわけではないって意味ね。)
動く子は、分かってないけど性格的に動ける子なのだろう。
性格だ。
高学年以降の動かない子
じゃあ、小学校高学年以降でも動かない子はどうでしょうか。
いますよね。
自分で管理できるハズの年齢なのに、できない(やらない)子。
これは、理由を考えた方がいいと思う。
能力的にはできるハズ。
じゃあ動かない「理由」があるハズだ。
例えば、ADHDだとタスク管理が非常に、非常に! 苦手だったりする。
その場合はタスクを減らしたり、大人がフォローするとか。
また、知的にゆっくりな可能性も。
これも丁寧に説明したり、選択肢を減らす方が良い。
経験的に多いのが、二次障害だ。
今まで、できないできない言われ続けた子。
叱られ、けなされ、否定され続けてきた。
もしくは、
こんな感じ。
二次障害ですね。
これが厄介。
本人のモチベーションがないので、支援も困難。
だったら、バトルになるくらいならいっそのこと「親が全部やる」か「親は介入しない」の方がよいと、僕は思うわけです。
まとめ
できる子とできない子の違いは、そこまで大きくない。
と思う。
できる子が、とてつもなく優れているわけではない。
と思っている。
単なる性格
によるところも大きそうだ。
逆に言うと、出来ない子がそこまで劣っているわけでもない。
今出来ないからといって焦る必要もないだろう。
きっとそのうちできる。
納得しないと動けない派の僕としては、ふわっと動ける人たちが羨ましいけどね。
もう、これが自分(我が子)と思って受け入れるしかないのでしょうね。
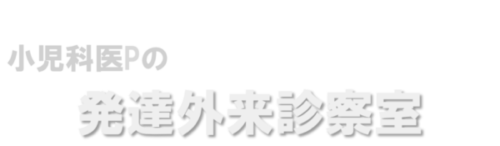







うちは中1息子、二次障害です。
しかも反抗期、手出し口出しはできないので
「介入しない」でいいですね。
安心してほっておけます。ありがとうございます。
私は優等生タイプでしたが、テストで分からなかったらドキドキする、先生に怒られたら嫌だからくらいの理由で勉強していたように思います。
大学生や社会人になって、自分は何がしたいのか、分からなくなりました。言われたことはちゃんと出来るので世間の評価は良いのですが、趣味や好きなことが分からなくてプレやすかったです。
ちゃんと好き嫌いがある人は凄いな、強いなぁと思います。いつも好きなことに熱中している長男、変わった感性を持っている次男がいるので、改めて多様性を感じています。
今週の小3息子の音読は、金子みすゞ。「みんな違ってみんないい」暗記するほど親子で唱えています。
いつも、本当に本当にありがとうございます。先生のブログがなかったら、どうなっていたやら、、です。
今回の記事と、以前の記事をあわせての疑問です。
我が家の暴走男子(小2)、
・やらないといけない(と言われている)ことはわかっている
・やるつもりはない(やりたくない)
なので、
・言われたこととは別の、自分のやりたい事をやる
という感じです。
学校の先生達からは、それが『衝動性』と判断され、投薬推しが強いです。
でも、親目線では、「やるつもりがない」のをひしひしと感じるので、薬を飲んだからって、やるのかな??
と疑問です。
成長して、「とは言え、イヤでもやらないといけない事はある」と納得したら(諦めがついたら)いつかはやるのではないかと思っていますが、こんなタイプでも、「案外薬が効くこともあるよ、試してみれば?」ということもあり得るものでしょうか?
機会がありましたら、教えてください。
これからも楽しみにしています!
こんにちは!
そうですね。私は所謂 大人しい優等生タイプ に見られがちな子供でしたが、
自分の子供時代を思い出しても、
“あと先”を理解したうえで動いてた気はしません。
宿題忘れたら怒られる、
とか
忘れ物したらすごくドキドキしちゃうから忘れたくない、
くらいの勘定はあったけど。
忘れ物しても宿題やってなくても怒られても立たされても、
平気〜って感じのヤンチャ男子、羨ましかったなぁ。
鋼のハートを持ってるのかな、いいなぁ、と。
で、低学年の頃は「平気でいいなぁ」くらいだったけど、
高学年になって行く中で
「キチッとしてなくても死にはしない」を実感させてもらってました。
うちの小2娘の頭が融通きかなくなってる時は、そんな自分を思い出して接してます。